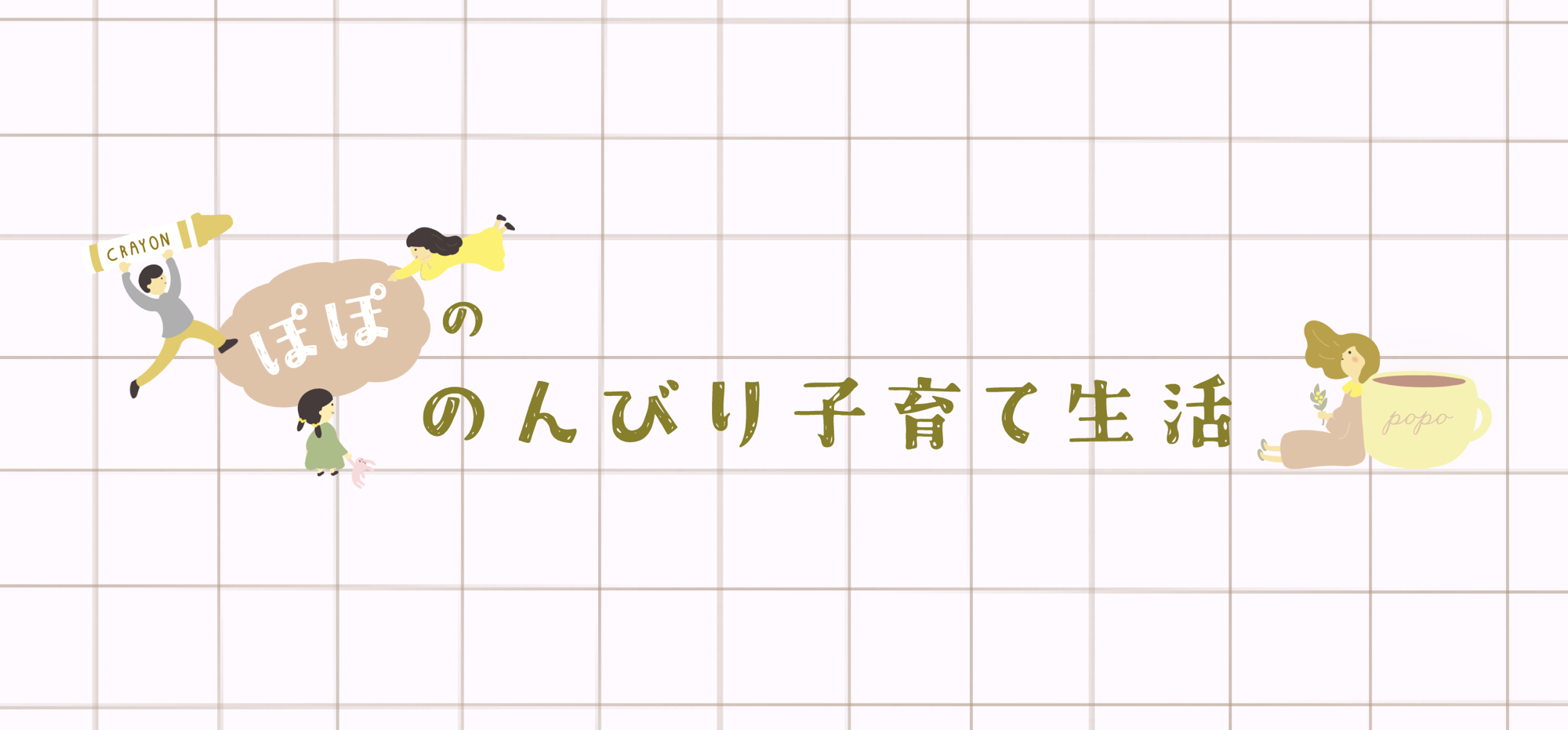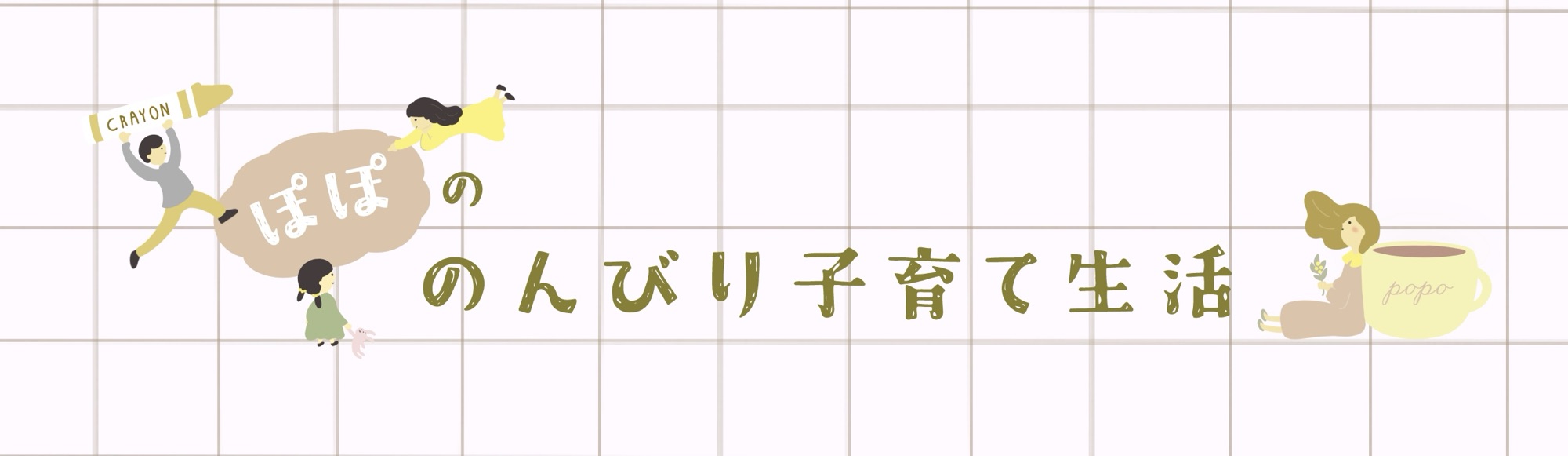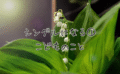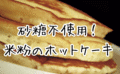離婚を決めるときに、一番心配だったのはお金のことです。
給料面では元夫の方が上で、しかも私は長期育休中だったので、今後金銭面でやっていけるのかどうか不安でした。
今回はお金に焦点を当てて、離婚前に考えたことなどを書いていきたいと思います。
こどもに不自由をさせないか
まず一つ目の不安は教育・養育費です。
前回の「①こどものこと」でも書きましたが、ある調査ではこどもを大学まで通わせると、一人にかかる養育費と教育費の合計は2700万円ほどと言われているそうです。
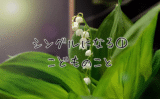
環境によっても変わりますが、かなりの額が必要になるのには変わりありません。
まずは、養育費として元夫から毎月いくら貰えるのかを確認しました。
養育費には裁判官が研究員となり、統計資料などをもとに司法研究・提案されている「標準算定方式・算定表(令和元年版)」があります。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
いくら貰えるかは自分の収入と相手の収入、こどもの数により大きく変わってきます。
また、この表は絶対ではなく、あくまで標準的な養育費を迅速に算出するためのものです。
実際の養育費はいろいろな事情を考慮して定まります。当事者間の合意でも、いろいろな事情を考慮して最終的な金額を定めることが考えられるので、結果的に増減することもあります。
また、残念ながら支払いが滞ってしまう場合もあるとのことなので、公正証書を作成して法的拘束力をもたせておくなど、できる対策はしておこうと思いました。
日々の生活費は稼げるのか
出産前は教員として働いていたのですが、長男〜次女の出産まで、ほぼ連続して産休・育休をとりました。
そして別居を機に地元に戻ってきたため、通勤距離の関係で一度仕事を辞めることになり、今回離婚すると決め、一から職探しをすることになりました。
地元でまた教員として働くことも考えました。
教師はやりがいのある仕事ですし、以前と比べると働き方も変わって、だいぶ働きやすくなっています。
しかし、どうしても時間外に外せない面談を入れざるを得なかったり、こどもの体調不良が続くと、特に担任の場合は休みづらさがあったりと、シングルが働く環境としては少し厳しいように思います。
そこで、教員の臨時講師として数時間だけ学校で働きつつ、在宅でできる仕事を探して挑戦してみようと考えています。
こどもたちの成長とともに働き方も見直しつつ、安定した職に就けるようにしようと思います。
固定費の見直しや、受けられる支援の種類などについても調べました。
後日他の記事にまとめるので、そちらもぜひご活用ください。
老後の資金を貯められるか
二つ目は老後の資金についてです。
かなり前に「老後2000万円問題」が話題になったのを覚えている人も多いと思います。
「老後2000万円問題」とは、2019年に金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループが発表した報告書の中で、高齢夫婦無職世帯が老後30年間で約2000万円不足する可能性があると指摘されたことから話題になった問題です。
「2000万円」という数字は試算されたものです。
平均的な高齢夫婦無職世帯の収支を基にしているため、個々のライフスタイルや収入、支出によって必要な金額は大きく異なります。
しかし、年金だけでは老後の生活費を賄えないため、若いうちからの資産形成の必要性を示したという意味で、大きなインパクトがありました。
「夫婦2人で」というのが試算の前提にあります。
独身世帯では使うお金も少ないものの、世帯の年金収入も低くなることが考えられます。
また、賃貸住宅に住み続ける場合や、介護が必要になったりする場合は、より多くの資金が必要になります。
シングルマザー(ファザー)の場合は、フルタイムで仕事ができないことも多く、貰える年金が更に減ってしまうことも考えられます。
日々の生活費で手一杯になってしまいそうで不安ばかりが募ります。
しかし、現在は無料で使えるライフプランシュミレーターや生活費のシュミレーターが様々あるため、それらを活用してシュミレーションすることで漠然とした不安は消せるのではないかと思います。
もしも金額が足りないという場合は、支出の見直しや公的な支援なども考える必要があります。
財産分与や養育費、慰謝料の金額
実際手元にいくらお金が残るのかによって、これからの生活を想像しやすいと思います。
子どもたちのためにも自分の将来のためにも、貰えるものはしっかり貰って安心して生活できるようにしていくため、必要なことを調べました。
財産分与
財産分与とは、離婚時に婚姻中に夫婦で協力して築いた財産(+負債)を公平に分ける制度です。
名義にかかわらず、不動産、預貯金、有価証券、車、保険(解約返戻金含む)、退職金(婚姻中に発生したもの)、年金(分割対象)など、実質的に協力で形成されたものは対象になります。
結婚前に持っていた財産、相続・贈与で得た財産などは「特有財産」として分与の対象外です。
また、借金も対象になりますが、家計のために共同で増えた負債のみが含まれ、ギャンブルや個人的借金は原則対象外です。
収入・家事・育児などの貢献は同等とみなされつため、原則50:50で分割します。
財産分与の流れは、当事者間の協議 → 家庭裁判所の調停・審判 → 裁判となります。
離婚後でも請求可能ですが、離婚後2年以内に手続きをしないと権利が消滅します。
話し合いで決める場合は、しっかりと交渉をして後悔のないようにしましょう。
養育費
養育費については上でも少し書きました。
養育費とは、離婚などで親と離れて暮らす子どもが安心して成長できるように、もう一方の親が生活費などを支払うお金です。
衣食住、学校・教育費、医療費、交通費、習い事や娯楽など、子どもが「普通に暮らすため」に必要な支出に使われ、どもが「大人として自立できるまで」、一般的に18歳、進学がある場合は大学卒業などまで支払われます。
公正証書に残しておくことで、強制執行(給与や預金の差し押さえ)が可能になるため、必ず公正証書を作成しましょう。
詳しくは、養育費の取り決めをしたときの記事に書きます。
慰謝料
「慰謝料」とは配偶者や他人による不法な行為で精神的・肉体的に傷ついたときの“おわび”のお金です。
慰謝料をもらえるケースは、不倫・浮気、配偶者への暴力(DV)などの場合です。
「性格が合わない」「価値観が違う」という「性格の不一致」だけでは通常は支払われません。
事情によって増減しますが、多くは100〜300万円程度です。
私たちの場合はお互いに有責事項がなかったため、特に慰謝料は発生しませんでしたが、何か当てはまることがあれば必要に応じて慰謝料請求しましょう。
受けられる支援
もしも生活が厳しくなったときのために、ひとり親家庭が受けられる手当などについても事前に調べました。
また別の記事に書くので、そちらもぜひ確認してください。
自信をもって生活するために
大切なのは知識です。
知識がないと、漠然とした不安がありなかなか離婚に踏み切れなかったり、貰えたはずのお金なのに貰えず損をしてしまったりします。
知ることで、できることが増えたり、反対に無謀なことに気付けたりもします。
今の状況をより良くするためにも、知ることを怖がらず、めんどくさがらず、情報を集めていくことが必要です。
私も調べた情報をわかりやすく発信していくので、共有していきたいと思います。
次はメンタル面についての不安について、よろしければお付き合いください。