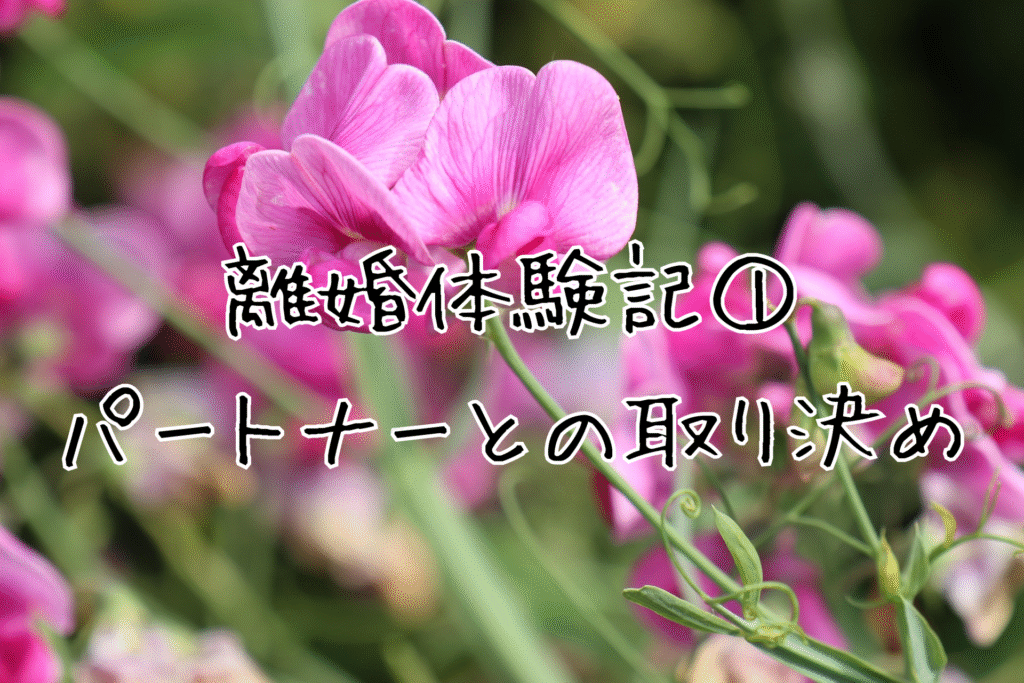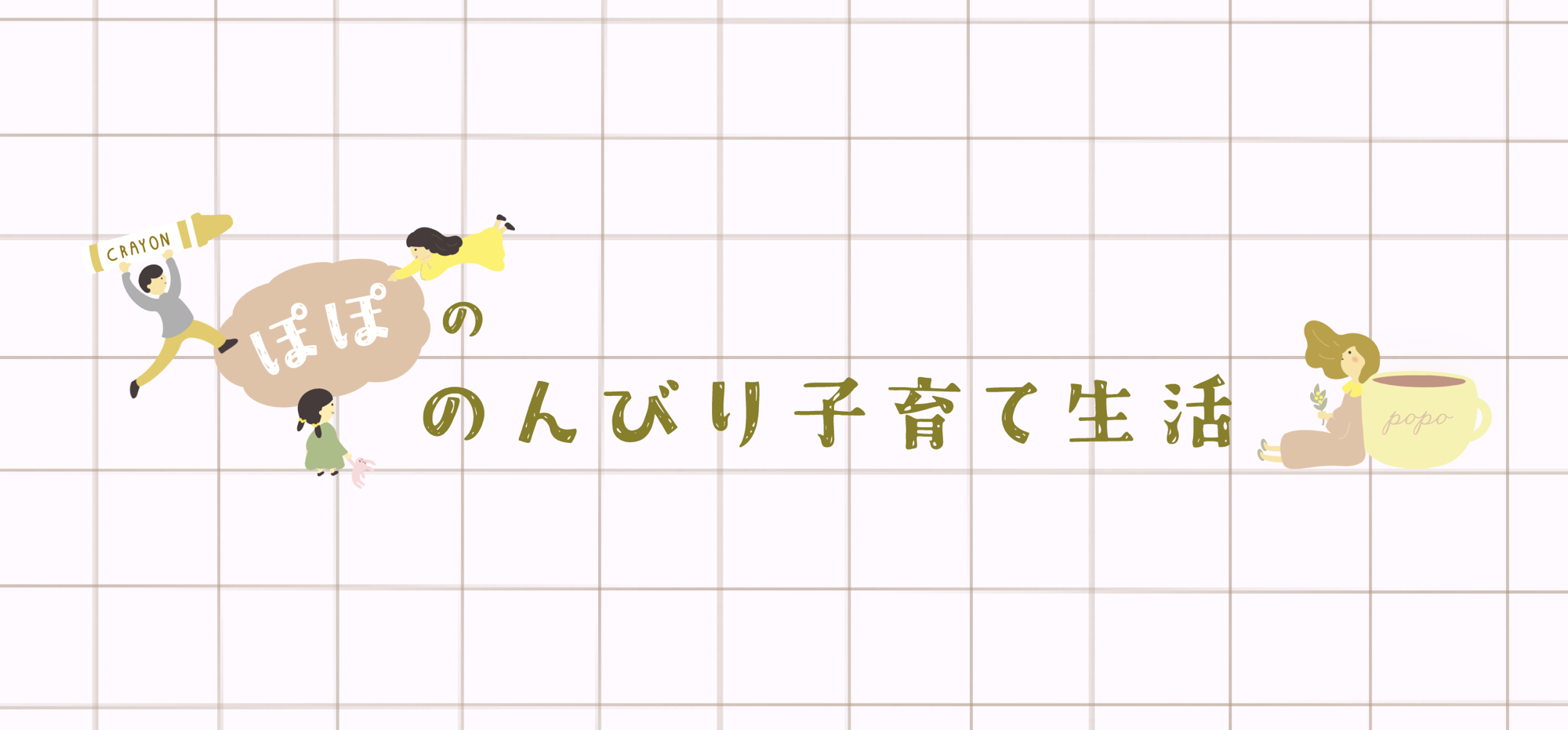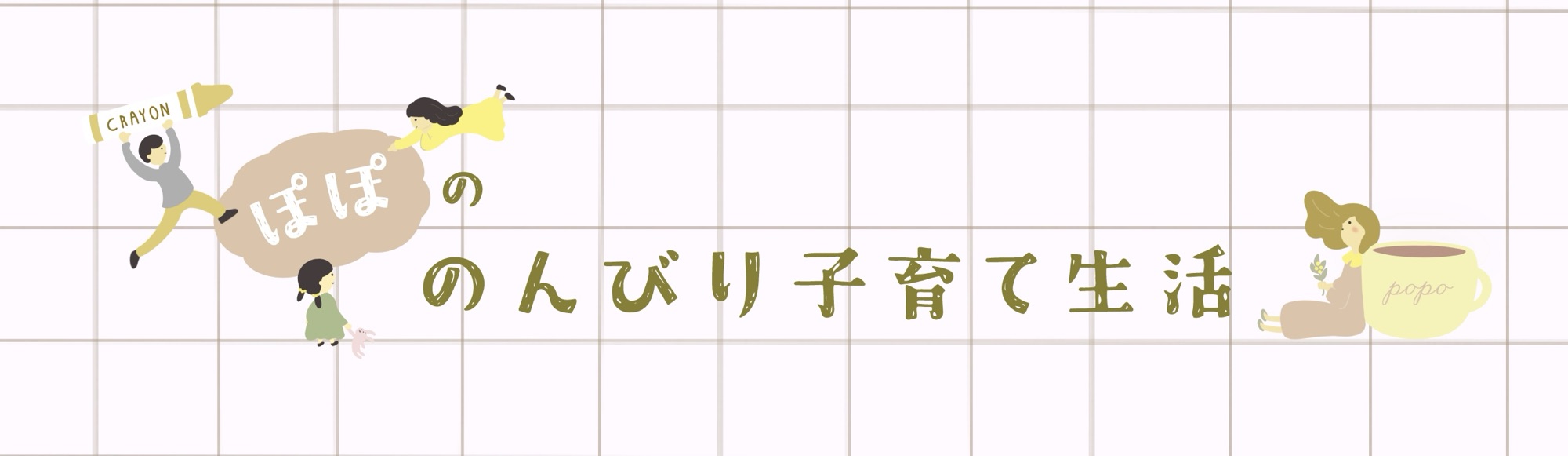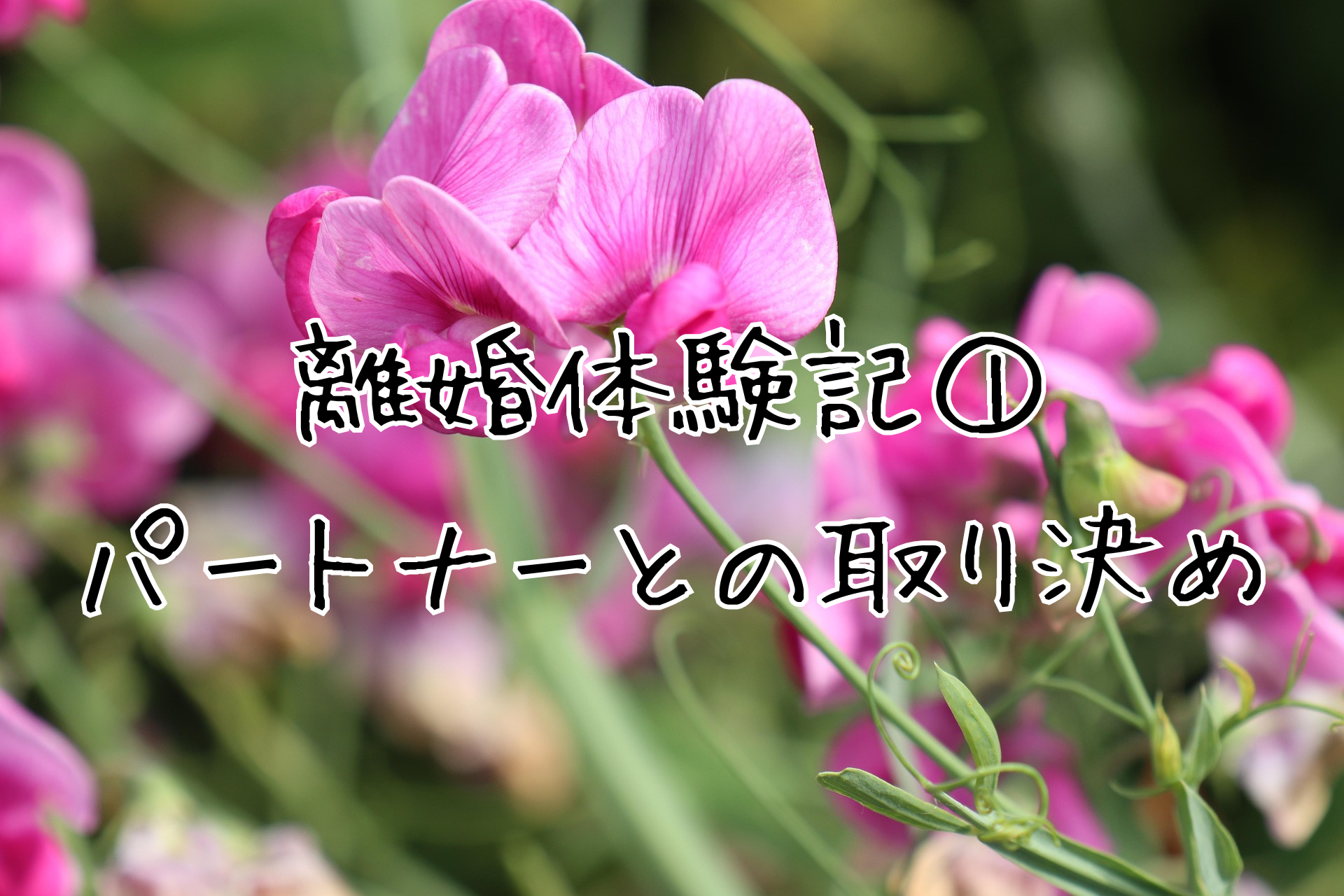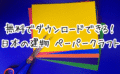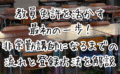私は2025年、こども3人を連れて離婚しました。
その前に2年間別居し、お互いの気持ちが離れていたこと、相談事項で特段揉めなかったこともあり「協議離婚」という形で離婚しました。
話し合いは基本的にLINEを使って記録を残しながら進めました。面と向かうと感情的になりやすかったこと、後から「言った・言わない」とならないようにしたかったためです。
今回は、離婚するまでの協議の内容について書いていきたいと思います。
親権のこと
まずはお互い、親権獲得の意思があるかを確認しました。
結果はお互い親権獲得の意思あり。
けれど私が3人を連れて家を出ていたことと、別居するまでの育児もほぼ私がやっていたことで、このまま争っても元夫が親権を獲れる可能性はかなり低そうでした。
そのため、かなりあっさりと相手が折れました。
実際のところ、元夫側はパフォーマンスだったのかもしれません。
口では親権が欲しいと言っていたけれど、実際育てることになったら難しかっただろうと思うので、恐らく最初から、とれないだろうと分かった上で、体裁上「親権は欲しい」と言っていただけのように思います。
親権は私が持つことに、すぐ決まりました。
面会交流
元夫からは 面会交流 を求められました。
危害を加えるタイプではなかったため、私は相手の希望を受け入れました。
- 月1回程度の面会
- 長期休暇中の外泊を伴う交流
- 相手方の親族に会わせること
これらを承諾しました。
養育費
離婚するまでも、養育費は別居して1年経った頃から算定表をもとに貰っていたので、それをもとに、今後の収入の増減を加味した金額で合意しました。
また交渉して、毎月の養育費以外にも、子どもの入学時に一時金を加えて用意してもらうことになりました。
養育費と学費は別物
ここで大切なのは「養育費と学費は別」という点です。
養育費=子どもの基本的生活費+義務教育に必要な費用。
学費(特に高校・大学など任意進学の費用)は原則「別扱い」です。
こどもが小さいうちは私がフルタイムで働くことは厳しいかもしれないと思っていたので、学費を貯めることが難しいかもしれないと感じていました。
そのため元夫から、学費をできるだけ多く貰えるよう、話し合いを重ねました。
離婚する、もしくは離婚した相手と話し合うのは精神的にも辛いかもしれませんが、養育費や学費についてはこどもたちのためにも妥協せず、粘り強く交渉することが大切です。
慰謝料
今回、私にも相手にも特にこれといった明確な有責事項があったわけではないため、慰謝料の請求はありませんでした。
不貞行為やDVなどがきっかけで離婚する場合には、しっかりと慰謝料を請求しましょう。
必要があれば、弁護士を通して話をする方が良いこともあります。
自治体で無料の相談会や、弁護士費用の補助などがあることがあるので、調べてみることをお勧めします。
財産分与
財産分与は主に「夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配」をするための制度です。
結婚後に夫婦が協力して築いた預貯金、不動産、車、株式、退職金(条件あり)などの「共有財産」が対象で、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得たものは原則として対象外となります。
分け方の原則は2分の1ずつ(半分ずつ)ですが、話し合いで割合や方法を自由に決めることも可能です。
まずは夫婦間で協議します。
そこで話がまとまらなければ、家庭裁判所で「調停」→「審判」の順に進みます。
私の場合は一緒に住んでいたところが持ち家、元夫の単独ローンだったため、家を査定してもらいました。
ちょうど地価や物価が上がった時期だったので、10年前の物件でしたが、ほぼ当時と変わらない価値があることがわかりました。
返済もかなり終わっていたため、そこに元夫がそのまま住む代わりに、貯金などを私が多めにもらうという形で話がまとまりました。
話し合いにお金をかけたくなかったため、できる限り自分たちで話し合いました。
話し合いの最中はかなり消耗しましたが、
財産分与は離婚後、2年以内に請求しないと権利が消滅してしまいます。
2年間はバタバタしていると意外とあっと今に過ぎてしまうので、忘れないうちに話し合い、請求することが必要です。
また、相手が信用できない場合や金銭の持ち逃げなどが心配される場合は、離婚の手続きの前に財産分与を済ませておくことをおすすめします。
公正証書
取り決めは公正証書に残しておきましょう。
公正証書とは公証人が第三者の立場から内容と有効性を証明する契約書です。
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
引用:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01 日本公証人連合会
公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。
また、金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
私の場合は離婚後に公正証書を作成したのですが、離婚してからも連絡を取り合って内容を確認したり、顔を合わせて一緒に公正証書を作ったりというのがかなりストレスでした。
できるなら、離婚前に全て終わらせておく方が良かったと思っています。
また、離婚後に公正証書を作りたくないと言い出される可能性もあります。
これは相手の協力がないと難しいので、相手が信用できないときなどは特に、必ず離婚前に作成しましょう。
例えば養育費の支払いが滞った場合、口約束だけだとそのまま泣き寝入りすることにもなりかねません。
公正証書に「強制執行認諾条項」が入っていれば、養育費や慰謝料などの金銭支払いが滞った場合に、地方裁判所に「強制執行の申立て」をして、相手の財産や給料を差し押さえることができます。
これは裁判を起こさなくても、すぐに強制執行の手続きに移れるという大きなメリットがあります。
もちろん、自分の側も公正証書で取り決めた約束などは守らなければいけませんが、こどもを養育する側はぜひしっかりと内容を確認して、公正証書を作成してください。
まとめ
協議離婚は「お金のこと」「子どものこと」「財産のこと」をすべて話し合って決める必要があります。
- 親権は子どもと一緒に過ごしてきた方が有利
- 面会交流は子どもの利益を最優先に
- 養育費と学費は別物、粘り強く交渉を
- 財産分与は2年以内に請求
- 公正証書は離婚前に作成、強制執行条項を忘れずに
離婚はエネルギーを使う出来事ですが、子どもの将来のために、しっかりと準備し、必要なら専門家の力も借りながら進めることをおすすめします。