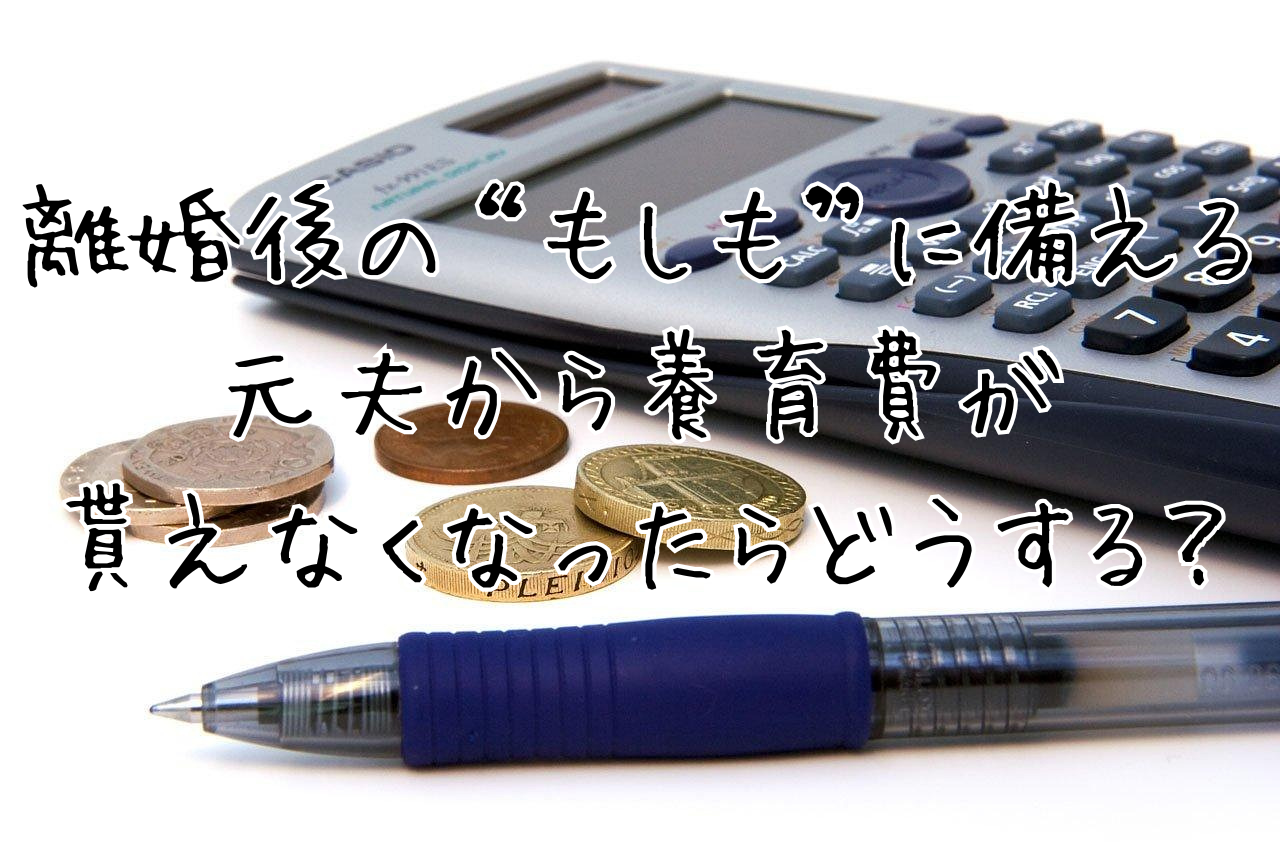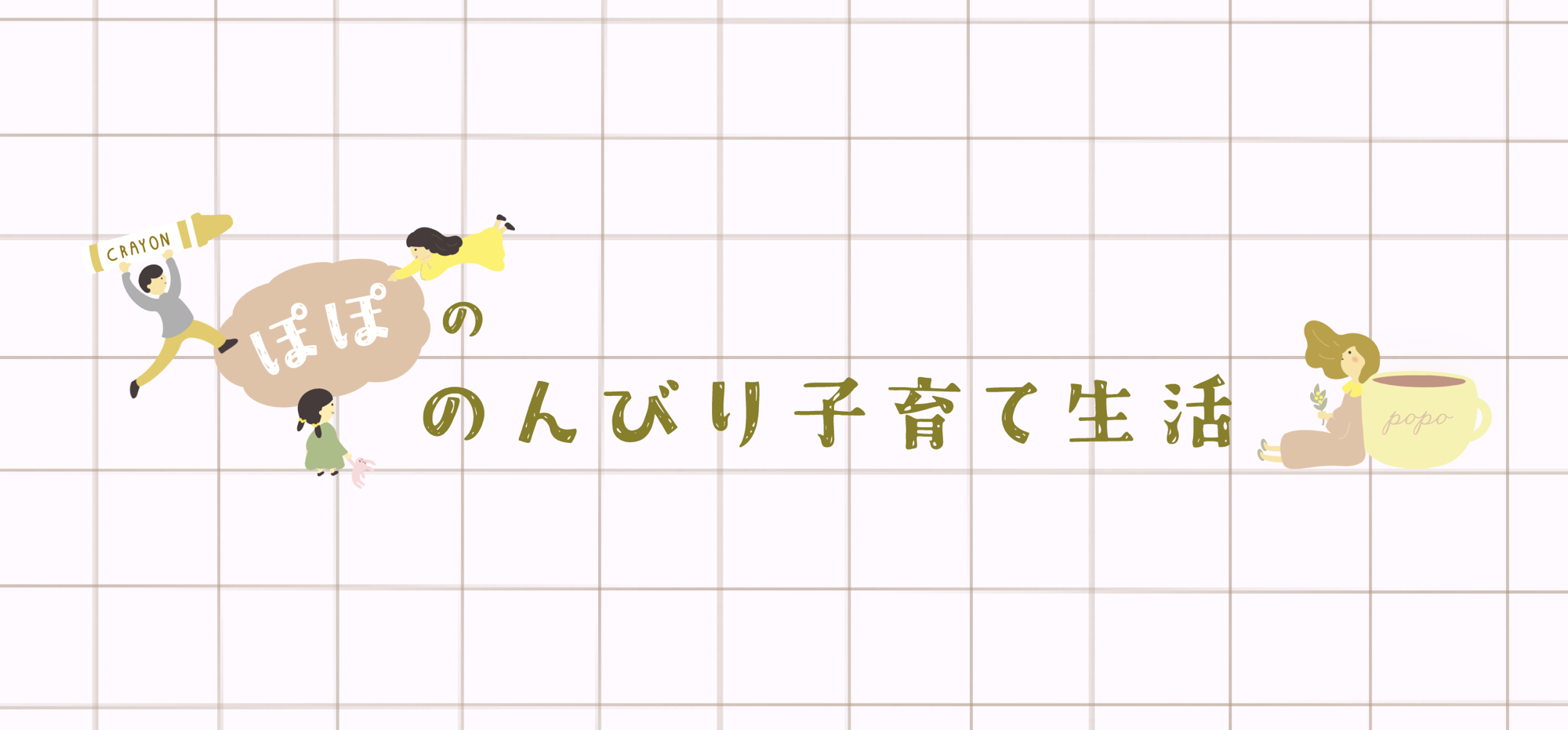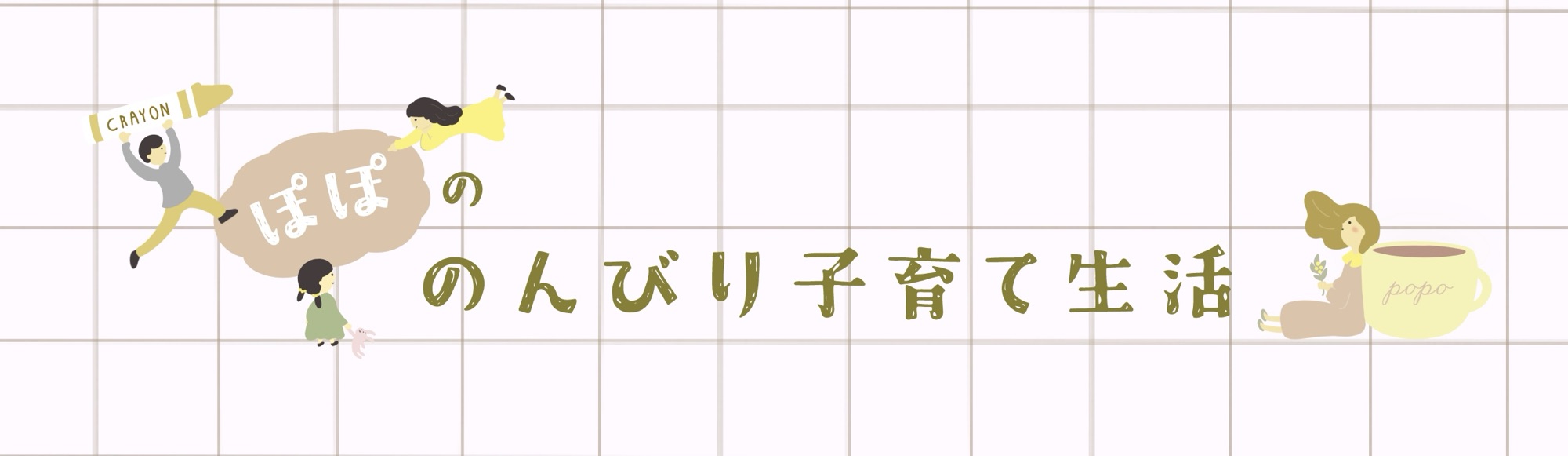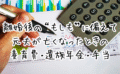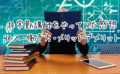離婚後、子どもを育てながら生活を支えるうえで欠かせない「養育費」。
しかし、元夫が失業したり、収入が大きく減ってしまった場合、養育費はどうなるのでしょうか。
実際、支払いが止まってしまうケースや、金額の見直しを求められることもあります。
そんな“もしも”のときに知っておきたいのが、減額のルールや公的な支援制度、そしていざという時に頼れる手当の仕組みです。
この記事では、元夫の収入が途絶えたときに起こりうる養育費の変化と、その後の生活を支えるために知っておきたい制度について、わかりやすく解説します。
元夫が失業・収入減になったとき、養育費はどうなる?
離婚後、毎月決まった金額の養育費が入ってくることで、なんとか生活の見通しが立っていた——。
そんな中、元夫から「仕事を辞めた」「収入が減った」と言われたら、どうなるのでしょう。
「このまま養育費が止まってしまうのでは…?」と不安に思う方は、多いはずです。
まず知っておきたいのは、養育費は元夫の収入が減ったからといって、自動的に支払い義務がなくなるものではないということ。
たとえ失業しても、家庭裁判所での手続きなしに支払いを止めることはできません。
養育費は子どもの権利です。
支払いが滞った場合は、きちんと手続きを踏んで請求することができます。
たとえば、離婚時に公正証書や調停調書で養育費の金額を決めている場合、一方的に「もう払えない」と言われても、それは法律的には無効です。
支払いを減らしたい・止めたい場合は、家庭裁判所に「養育費減額の申立て」を行う必要があります。
何かあった場合、焦って感情的に話し合うよりも、まずはルールを知ることが第一歩。
事前に「法律でどう定められているか」を理解しておくことで、無用なトラブルを避けることができます。
養育費の減額が認められるケースとは?
元夫が「収入が減ったから養育費を下げたい」と言ってきたとき、必ずしもそれが認められるとは限りません。
養育費の金額の変更は“やむを得ない事情”があると家庭裁判所が判断した場合に限られます。
たとえば、次のようなケースでは減額や一時的な免除が認められることがあります。
- 勤務先の倒産やリストラなど、本人の責任ではない失業
- 病気やケガなどで長期間働けなくなった場合
- 再婚や新しい子どもの誕生によって生活費のバランスが大きく変わった場合
反対に、以下のような場合は、減額が認められにくいです。
- 自己都合で退職した、転職活動中である
- 一時的に残業が減った、ボーナスが減ったなどの軽微な減収
- 新しい趣味や事業など、本人の選択による支出増
家庭裁判所では、「子どもの生活水準を維持できるかどうか」が重視されます。
つまり、支払う側の事情よりも、子どもの利益が最優先。
また、申立てが認められるまでは、原則として今までの金額を支払う義務が続きます。
「申立て中だから払わなくていい」というわけではないので、支払いが滞った場合はあとから請求できる場合もあります。
私の周りでも、元夫の失業をきっかけに一時的な減額調停を行ったケースがありましたが、最終的には「就職後に支払いを再開する」という条件付きで調整されていました。
もし相手から減額を求められた場合は、決して感情的にならず、理由を確認し、書面でやり取りを残すことが大切です。
支払いが止まってしまった場合の対応策
元夫が「収入がなくて払えない」と言ったきり、養育費の振り込みが止まってしうと、どうすればいいのか分からず不安になります。
「催促してもいいの?」「関係が悪化するのでは…」と迷うこともあると思います。
しかし、放置してしまうとそのままになってしまう可能性もあるため、何らかのアクションを起こすことが必要です。
話し合いと内容証明で意思を示す
最初のステップとして、元夫に「支払いが止まっていること」「再開を求めること」を
内容証明郵便などで正式に伝えましょう。
電話やLINEだけのやり取りだと、後から「言った・言わない」で揉めやすくなります。
履行勧告・強制執行という法的手段もある
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立てることができます。
これは、裁判所が相手に「支払いを履行するよう勧告」してくれる制度です。
それでも払われないときは、給与の差押え(強制執行)を申し立てることも可能です。
特に「調停調書」や「公正証書」で養育費の取り決めをしている場合、その文書自体が強制執行できる法的な証拠になります。

公正証書に残しておくのが大切なのは、こういうときのためだね。
養育費保証サービスを利用する方法も
最近では、養育費の滞納リスクに備えて「養育費保証サービス」を利用する方も増えています。
これは、相手からの支払いが滞った場合に、代わりに立て替えて支払ってくれる民間サービスです。
自治体によっては、このサービスを導入している地域もあります。
自治体の支援も忘れずに
市区町村によっては、「養育費確保支援事業」や「法的相談窓口」を設けていることもあります。
無料で弁護士に相談できるケースもあるので、一人で抱え込まずに活用してみてください。
私自身、最初は「請求するなんて気が引ける」と思っていましたが、子どもの将来を守るために行動するのは、決して悪いことではありません。
大切なのは、「正しい手順で」「証拠を残しながら」進めること。
焦らず、でも確実に、次の一歩を踏み出していきましょう。
公的支援で生活を支えるには
相手の理由が認められ、養育費の減額や停止などが決定してしまった場合は不安も大きいと思います。
けれど、ひとり親家庭には国や自治体が用意している支援制度がいくつもあり、知っているかどうかで、家計の安心感がまるで違います。
児童扶養手当
もっとも基本的な支援が、この「児童扶養手当」です。
18歳になった最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の子どもを育てている場合に支給されます。
支給額は所得によって変わりますが、2025年度の目安では、
- 全部支給:約4万4,000円(子ども1人)
二人目以降は ずつ支給。 - 一部支給:所得に応じて減額
となっています。
自治体によっては、申請手続きをオンラインで受け付けているところもあります。
児童手当
こちらはすべての家庭が対象ですが、ひとり親家庭にとっても大切な収入源です。
0歳から高校卒業までの子どもに支給され、
- 3歳未満:1万5,000円
- 3歳〜中学生:1万円(月額)
が基本です。
住宅手当・就学援助制度
自治体によっては、母子家庭・父子家庭に対して家賃補助(住宅手当)を設けている場合もあります。
また、学校関係の支出が大きい時期には、就学援助制度を利用するのもおすすめです。
給食費や学用品代が一部または全額補助される制度で、申請は各学校や市区町村の教育委員会で行えます。
その他のサポート
- ひとり親家庭等医療費助成(医療費の自己負担が軽減)
- 高等職業訓練促進給付金(資格取得を支援する給付金)
- 母子・父子福祉資金貸付金(生活資金や進学費用の貸付)
これらを組み合わせることで、養育費が一時的に途絶えても、一定の生活を保つことができます。
私も最初は「手当なんて複雑そう」と感じていましたが、市役所の「ひとり親家庭支援窓口」で相談したところ、丁寧に案内してもらえました。
勇気を出して相談してみるだけで、受けられる支援がぐっと広がります。
“もしも”に備えて今からできること
養育費は、毎月の生活を支える大切なお金。
でも、相手の収入や体調、環境の変化によって、いつ・どのタイミングで支払いが途絶えるかは分かりません。
私自身も、離婚当初は「決めた金額がずっと続くもの」と思い込んでいましたが、現実にはそう簡単ではないことを実感しました。
だからこそ大切なのは、「もしも」の備えをしておくことです。
ここでは、私が実際に調べたり行動してよかったと思うことを紹介します。
養育費の取り決めは「書面」で残しておく
口約束のままだと、相手の都合で支払いが止まってしまっても、法的に請求することが難しくなります。
公正証書または家庭裁判所の調停調書として残しておけば、万が一支払いが滞っても、強制執行(差押え)が可能になります。
養育費保証サービスを検討する
最近では、養育費を保証してくれる民間サービスも登場しています。
相手が支払えなくなった場合でも、保証会社が代わりに立て替えてくれる仕組みです。
自治体によっては、契約費用の一部を補助してくれるところもあります。
いざというときの安心材料として検討する価値があります。
生命保険や学資保険で「万一のとき」に備える
元夫が支払い途中で亡くなってしまった場合などは、未払い分の養育費は相続財産として請求できる可能性がありますが、実際は簡単ではありません。
だからこそ、自分自身の備えとして保険を活用しておくことも大切です。
学資保険や低解約返戻金型の生命保険など、無理のない範囲で「子どもの将来資金」を確保しておきましょう。
行政の支援を定期的にチェック
ひとり親向けの制度や助成金は、年度ごとに変更されることがあります。
市区町村のホームページや広報誌を定期的にチェックしておくと、思いがけないサポートを受けられることもあります。
離婚後の生活は、どうしても不安がつきまといます。
けれど、「知ること」と「備えること」で、心の負担はぐっと軽くなります。
いざというときに慌てないように、今のうちから少しずつ準備していきましょう。